私の糖尿病50年-糖尿病医療の歩み
22.ステロイド糖尿病
1. 奇跡のホルモン剤の発見
第二次大戦中は海外の文献は入ってこない状態が続いた。終戦後は少しずつ入って来たが、大都市にはアメリカ文化センターができその図書館で医学雑誌も読めた(No.4参照)。さてもっとも劇的だったのは副腎皮質ホルモンの効果であった。昨日まで歩けなかったリウマチの患者がコーチゾン服用で痛みがなくなり歩けるようになったなどのニュースが伝わってきた。その発見にかかわったアメリカのKendallとHenchそしてスイスのReichsteinは1950年度ノーベル賞を受賞した。50年代になるとそれらのステロイドホルモン剤が輸入されて日本でも使用できるようになった。リウマチ以外にも白血病、再生不良性貧血、腎疾患など多くの内科疾患に用いられ著効を奏した。ペニシリンとともに奇跡的な薬であった。それまで使用されていた薬は効用のはっきりしたものはなく気休め薬のようなものであった。しかし繁用されるとともに副作用もまた多く報告された。その1つがステロイド糖尿病であった。米国ではLukens教授のネコのステロイド糖尿病の研究を手伝ったのでステロイド糖尿病は興味を惹くテーマであった(No.13参照)。東北大学第三内科でも血液疾患などでステロイドを使い、糖尿病になったから治療してくれという症例が多くなった。
2. ステロイド糖尿病の調査
第6回日本糖尿病学会が大阪で開かれそのシンポジウムでステロイド糖尿病を担当することになった。そこでわれわれは教室の症例とともに全国のステロイド糖尿病の状況を知るために、1962年に全国の大学病院の内科・小児科教室に調査表を送りそれを集計することを行った。当時はこのような全国のアンケート調査が各分野で盛んに行われた。そのときの成績は現在とのよい比較になっている。調査時東北大学の内科・小児科でステロイド治療を受けたのは628例で、そのうち治療後にはじめて糖尿病になったのは46例(7.3%)であった。糖尿病発症までに使用したのステロイドの総量をみると、1000mg以内のものでは454例中24例(5.0%)、1000〜2000mgのものでは88例中8例(9.1%)、2000〜5000mgのもの69例では10例(14.4%)、5000mg以上投与例では17例中3例(17.6%)と、投与量が多くなるほど糖尿病の頻度は高くなった。平均1日投与量では5mg以内では46例中4例(8.7%)、5mg以上10mgまで176例では8例(4.4%)、11mg以上20mgまで266例中19例(5.2%)、21mg以上30mgまで100例中10例(1.0%)、31mg以上50mgまで31例中3例(10%)、51mg以上9例中2例(22%)と投与量が増すにつれて出現頻度が増す傾向がみられた。投与日数の明らかな600例のうち糖尿病となった46例の糖尿病発現日数の累積頻度をみると図1のように90日までに65%となり300日までに約85%、540日で100%となっている。全国大学集計では90日までに66%、300日までに92.4%となっている。
|
図1 ステロイド糖尿病発症累積頻度
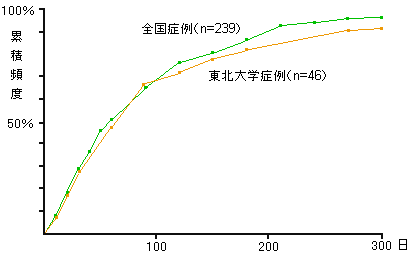
|
東北大学症例について年齢別発生頻度は表1のように40歳以後に高くなる。
|
表1 年齢別ステロイド糖尿病発症頻度(東北大学内科・小児科)
|
3. 糖尿病になりやすい疾患はないか
ステロイド療法で糖尿病になりやすい疾患はないだろうか、それを知りたいと思い図2〜4のような集計を行った。
|
図2 ステロイド糖尿病発症例の原疾患の症例数と総例に占める割合(%)
(全国大学内科教室例) 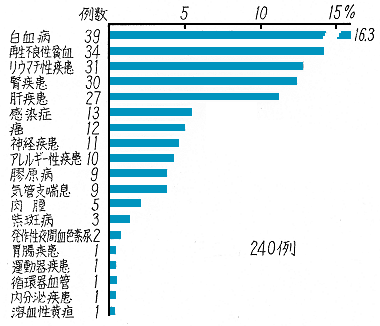
|
|
図3 糖尿病が発見されるまでのステロイド投与総量(疾患別)
(全国大学内科教室例) 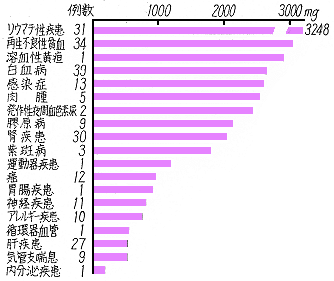
|
|
図4 糖尿病が発見されるまでの日数の疾患別平均値
(全国大学内科教室例) 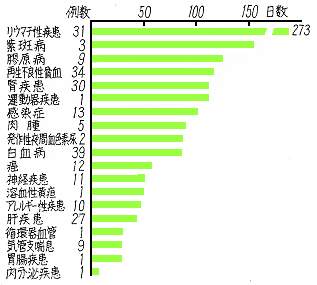
|
これらの図をみると特に発症しやすい疾患はなく、ステロイドの投与量と期間が多く長くなる疾患といえるように思われた。肝障害例では発症しやすいが、これは肝の分解・解毒機能の低下によると思われ、再生不良性貧血では膵にも血鉄症がみられ、線維増殖、腺房細胞の萎縮があり、その間に膵島が点在するのがみられた。ラットについても実験を行ったが糖尿病は現れなかった。
4. 転帰と治療は
ステロイド療法では食欲もすすむ。食事制限しても差し支えない病気のときは制限する。それでもコントロールできないときはインスリン療法を行う。ステロイドの効いている日中から夕食後にかけて血糖が上昇するので速効性インスリンで対応すればよい。現在なら超速効性インスリンをやればよく、ステロイド減量によって軽快したらインスリン量も減量すればよい。全国集計で転帰の明らかなもの212例では、ステロイド中止後の糖尿病は消失53%、軽快25.5%、不変12.5%、悪化3.8%。死亡3.8%、観察中1%であった。ステロイド中止によって糖尿病も消失するものをidiosteroid diabetes、中止後も持続するのはmetasteroid diabetesである。後者は糖尿病の素因のある症例が多い。
研究の詳細はホルモンと臨床 11巻3号、1963年、糖尿病 6、12-20、1963年参照。第5回IDF(トロント、1964年)でも発表。 (2004年10月03日更新)
※ヘモグロビンA1c(HbA1c)等の表記は記事の公開時期の値を表示しています。
Copyright ©1996-2024 soshinsha. 掲載記事・図表の無断転用を禁じます。
治療や療養についてかかりつけの医師や医療スタッフにご相談ください。

 医療・健康情報グループ検索
医療・健康情報グループ検索