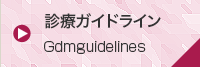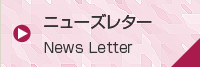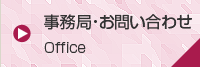会報 2005 October Vol.7 No.2
【巻頭言】
fatal Programmingの概念を考慮した
妊婦の体重管理と児の長期予後
森川 肇
奈良県立医科大学名誉教授、若宮病院顧問
1980年頃から男女児ともに平均出生体重は減少する傾向が認められ、一方では低出生体重児(出生体重2500g未満)の割合が著増しているが、低出生体重児が増加した要因の一つに母体の栄養代謝管理の影響が考えられる。食習慣の欧米化や経済成長に伴い、日本国民の栄養状態は劇的な変化を遂げ、摂取カロリーと動物性脂肪摂取の増加により肥満女性が増えているが、肥満妊婦では母児ともに周産期異常の発生が多いことが知られており、妊婦健診では妊娠に伴う体重増加を抑制するような栄養指導が一般的となっている。しかし、最近では10〜20歳代の女性に極端なダイエットを実行している者が多く、生殖年齢として重要や時期に"やせ"女性が倍増しており、若年女性に見られる"やせ願望"とも言える過度の栄養制限が妊娠期間中にも実行されて、低出生体重児の増加と関連している可能性は否定できない。
一般に、高血圧、高脂血症、動脈硬化、糖尿病などの生活習慣病は食習慣や生活習慣の乱れが原因とされているが、最近の疫学調査で母体の低栄養や妊娠合併症による子宮内発育遅延(IUGR)児が、出生後に急速に体重増加するcatch upの時期を経て、成人後に肥満や生活習慣病を高率に発症することが明らかとなった(fetal programmingの概念)。すなわち、英国のHertford-shireで疫学研究では、男女ともに出生体重が低いほど冠動脈疾患による死亡率が高いことが示され、また本邦での3歳児を対象に検討した成績では「小さく生まれて大きく育った」群ほど血圧が高く、「大きく生まれて小さく育った」群ほど血圧が低かったという。
動物実験でも、低栄養状態にして飼育された妊娠ラットから生まれた仔ラットは、出生時の体重がやや小さく、成熟後に心臓血管病変を起こしやすくなる、脂質代謝異常、インスリン分泌あるいは耐糖能の異常を示す、などが認められ、母体の低栄養が原因となって発育障害の仔が出生し、発育・成熟した後に栄養・代謝異常が惹起されると報告されている。
胎児期に劣悪な低栄養状態に曝露されると、生存に有利に作用する遺伝子が強く発現して、低栄養状態に適合するように代謝の反応性を変える結果、胎児は生き延びるが、この遺伝子は出生後も機能し続けるために、肥満、2型糖尿病、高血圧、高脂血症などのリスクを増加させるように作用する。つまり、胎生期の栄養障害が中年期以降に影響を及ぼして生活習慣病を惹起すると指摘されているが(fetal origins of adult disease:FOAD・提唱者の名をとってBarker説と通称されている)、遺伝子の発現とは関係ないという説もある。いずれにしろ、これらの成績は胎児を低栄養環境に曝すことなく健やかに胎内で養育することの重要性を再認識させるものである。
糖尿病合併妊娠において、1型糖尿病の妊婦では血管障害が進行していると子宮胎盤循環の減少に伴い、低出生体重児の頻度が高くなることはよく知られているが、Baker説との関連についての追跡調査に興味が持たれる。また、本邦では2型糖尿病が多いために、妊婦の肥満と周産期における母児の異常の関連を考慮した母体体重の増加抑制に重点が置かれる傾向にあるが、fetal programmingの概念を考慮すれば、妊娠母体に対する栄養管理の多寡が出生時の若年期から成人における疾病発現にどのような影響を与えているのかに配慮した適切な栄養代謝の管理が望まれる。すなわち、関連のある診療科が協力して、非妊時の母体体格(やせと肥満)、妊娠に伴う体重増加、栄養素の比率などに配慮しながら、脂肪の蓄積が多い肥満女性や脂肪が少ない"やせ"女性に対して個別化した管理方式を学会として作成し、出生児の長期予後との関連性を分析する必要があろう。
診察室だより 北から南から
医療法人南昌江内科クリニック
南 昌江
私は、1988年に福岡大学を卒業後、すぐに東京女子医科大学糖尿病センターで、当時の平田幸正教授、大森安恵教授のもと、3年間糖尿病および内科の研修を受けました。その後福岡に戻って九州大学第2内科に所属し、公立の病院で7年間糖尿病の臨床経験を積み、1998年に福岡市で開業しました。
現在、毎月約1000人以上の糖尿病患者さんが受診されています。年齢層も3歳〜92歳と、幼児から高齢者までいらっしゃいます。そのうち217名が1型糖尿病の患者さんで、女性は143名です。これまでに13名の1型糖尿病の女性が、16人の元気な赤ちゃんを出産されました。中には3回出産された方もおられ、全例出産に成功しています。30年ほど前までは、糖尿病を持つ女性の妊娠・出産は大変だといわれていましたが、大森先生をはじめ多くの先生方のご尽力により、血糖管理をしっかりすれば、今では健康な女性とほとんど同じように妊娠・出産することが可能な時代になりました。
当院では、小児期発症の患者さんに、高校生くらいからサマーキャンプなどで妊娠の教育をします。教育をしていても計画妊娠できない場合もありますが、妊娠がわかったらすぐに福岡赤十字病院の産婦人科と連携をとって、健康な妊婦さんと同じように、出産直前まで外来管理を行っています。それまでなかなか血糖コントロールがうまくできなかった方でも、妊娠するとほとんどの場合、驚くほどよくなります。妊娠は、血糖コントロールには最も強力なモチベーションとなり、また女性を強くしてくれるものだと思います。
子どもの頃からみていた糖尿病の患者さんが、思春期の難しい時期を経て大人の女性となり、お母さんとなって赤ちゃんを抱く姿を見ると感慨無量です。そして、このような感動を一緒に味わうことができることに幸せを感じます。現在も妊娠中の患者さん、そしてこれから妊娠して母になるであろう患者さんたちはたくさんいらっしゃいます。これからも糖尿病を持つ女性が安心して出産し、女性としての豊かな人生を送るお手伝いができればと思っております。
【ヤングコーナー】
小児ヤング糖尿病治療の小児科から内科への移行の問題
内潟 安子
東京女子医科大学糖尿病センター教授/小児ヤング外来チーフ
小児期に発症した慢性疾患であれば、「小児科から内科への移行」はどの疾患であっても避けて通ることができない問題である。小児ヤングの時期に発症した糖尿病もしかり。昔から検討されてきた問題であるが、今なおこれに関する問題が解決されずに生じていることも確かで、これは古くて新しい問題といえよう。
内科サイドからみると、小児科から紹介されてくる患児の自立心が乏しいことだ。親まかせにしているとか、自分で血糖コントロールするという意識が弱い。インスリン注射量の調節どころかどのように効いているのかも知らない、何のために血糖測定しているのかわかっていない、などなど。血糖コントロールの良好でない患児が内科に転科してきて、あっという間に網膜症や尿中アルブミンの増加を来すことも珍しくない。「最近眼科診察を済ませた」という患児が初診にきても早めに眼科予約をすることにしている。
一方、小児科サイドからみると、内科医はよく話を聞いてくれない、1型糖尿病のことをよく理解していない(2型糖尿病と一緒にしているのではないかなど)、血糖コントロールに関してきびしいことをいわれてしかられる、やさしくない、高齢者ばかりで患児がじろじろみられてしまう、という患児の嘆きとともに患児が小児科にもどってくることになる。思春期の食欲旺盛な時期の子どもの扱いに慣れていない糖尿病専門内科医がいることは事実。2型糖尿病と同じ食事療法を1型糖尿病患児に強いてしまう内科医がいることも事実である。
糖尿病性合併症を発症させたくない、これは小児科医も内科医も患児も家族も全員の共通の認識だ。そうはいっても、合併症は20代、30代以降に発症するため、小児ヤングの時期はインスリンを注射できて元気に学校に行っていれば満足されてしまうのではないか。1型糖尿病患者が合併症を発症したら、それは医療者に責任がある。小児科医と内科医は連絡を密にして小児ヤングの患者を守らねばならない。女性は思春期過ぎには結婚、妊娠が控えている。待ったなしなのだ。