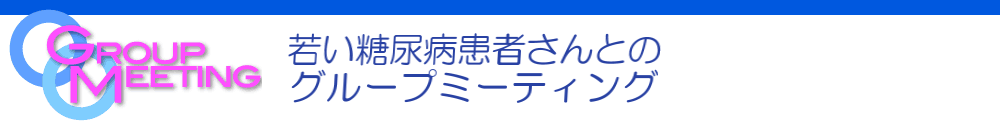第20回 若い糖尿病患者さんとのグループミーティングのまとめ
台風18号の影響で朝方はかなり強い雨が降っていましたが、28名の患者さんとその3名のご家族、8名の医師(うちスタッフ4名)、2名の看護師、2名の薬剤師、1名の検査技師、合わせて44名もの皆様にお集まりいただきました。
午前中はいつものように大きな輪となり、一言ずつ自己紹介や感じていることを話しました。
2週間前に1型糖尿病と診断されたお子さんとご家族が参加され、「本やインターネットで調べて知識は増えたが、この病気に関しては知恵をつけなければいけないと思った。」と参加の動機を述べてくださいました。確かにおっしゃるとおりだなと思いました。
食事やインスリン注射の工夫、低血糖の対処、いろいろな人生の出来事があったときの糖尿病との向き合い方、などは知識だけではどうしようもないことがたくさんあります。不安や心配は考えれば考えるほどつきません。
そのような時に、実際の体験談をきくことでどんなに心強くほっとすることでしょう。
毎日インスリンを注射し、そして孤独感でおちこんでしまうという方は "ここに仲間がいる。前向きになれる。"とおっしゃっていました。
病歴が長い方はご自分の体験を振り返りつつ"支援してほしい"と発言されました。ところが糖尿病は外からは見えません。傷が見えれば消毒をして包帯をして・・・とわかるのですが、どこに傷があるかが見えないのです。
病歴が長くなると糖尿病に関する知識もあるでしょうから、医療スタッフも新たに何が支援できるのかを戸惑うこともあります。
ですからその方は自分が何を支援してほしいのかを医療者はじめ周囲の人に具体的に伝える努力をしているとおっしゃいました。
互いにコミュニケーションをとることで、はじめて相手の状態がわかり、どのように支援できるのかがわかります。
診療の短い時間の中で医療スタッフができることは限られています。
ただ漫然と検査データを伝え、インスリンを処方するだけの外来診療にならないよう、患者サイドからはどのような支援を求めているのかを伝え、医療者はたえず聴くアンテナをたてていくことができればと思いました。
齋藤チャプレンによると、英語で医師"Medical Practitioner"というのは支援の専門家という意味だそうです。
1975年にジョンス・ホプキンス大学の医学部長は医学生に「どんな完璧な治療をしても、その患者さんの心に届かなかったとしたら不完全です。」と話したそうです。患者さんのニーズに沿った支援ができなければ、それは心には届かないと思います。
われわれ日本人には7年後の東京オリンピックという目標ができました。
7年後に自分がどこにいてどんな生活をしているかは自分自身が決められることです。
7年後の自分自身のために"血糖をコントロールしていくこと"の支援が必要でしたら、ぜひ感じていることを心の中にためこまずに周囲に伝えてみてください。