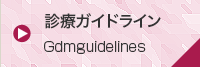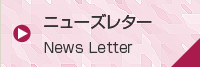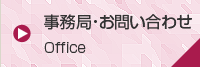会報 2009 October Vol.11 No.2
【巻頭言】
やせ妊婦—そのリスクとケア—
中林 正雄
母子愛育会愛育病院院長
はじめに
我が国では食生活の欧米化によって、肥満、2型糖尿病、高血圧の増加が問題となっているが、生殖年齢である20〜30代女性においては、やせ体型が増加している。平成19年国民健康・栄養調査によれば、20代ではBMI18.5未満のやせ体型女性は25.2%であり、成人女性全体におけるやせ体型は10.7%であるので、その2倍以上の高率である。これら生殖年齢にあるやせ体型女性では、栄養バランスに偏りがあることが多く、また、妊娠した場合でも普段の食生活が改善されず、妊娠中の体重増加が不十分なことが多い。このような"やせ妊婦"では、低出生体重児の発症率が高いことが知られている。
一方、20〜30代の生殖年齢にある女性ではBMI25以上の肥満は6〜11%であり、成人女性全体における肥満は20.2%であるので、生殖年齢の女性では肥満は少ないといえる。肥満女性が妊娠した場合は、妊娠中の体重増加の多少にかかわらず、妊娠高血圧症候群(pregnancy induced hypertension: PIH)、巨大児、帝王切開などの周産期異常が増加することが知られている。
やせ妊婦のリスクとケア
日本人の食事摂取基準(2005年版)によれば、20〜30代女性では妊娠期・授乳期におけるカロリー、カルシウム、鉄の摂取量は必要量、目安量、推奨量に比して著しく低値である。
愛育病院における正期産児(妊娠37〜41週、合併症のない単胎症例)の成績では、出生体重2,500g未満の低出生体重児の発症率は5%前後であるが、BMI18.5未満で、かつ妊娠中の体重増加量が5kg未満の妊婦での低出生体重児は21.7%もの高率であった。
妊娠中の体重増加が少なすぎると、低出生体重児以外にも、神経管閉鎖不全(二分脊椎、無脳児)などの奇形が増加するが、最近注目されているのは、胎児期成人病発症説(fetal origins of adult disease:FOAD, developmental origins of health and disease: DOHaD)である。1989年、イギリスのBarkerらは疫学調査にもとづいて、胎児期の母親の低栄養状態が成人病の素因になると報告した(Barker説)。
Barkerらは、胎児期の低栄養状態により、胎児の血管系、膵臓、腎糸球体、心臓などの諸臓器が発育不全となり、出生後の環境因子とあいまって、成人期に高血圧症、冠動脈硬化、2型糖尿病、腎疾患などが高率に発症することを報告しており、この現象は"胎児プログラミング"と呼ばれている。最近の研究によれば、長期間の子宮内の低栄養環境に対して、胎児の諸臓器が適応してエネルギー倹約型となり、遺伝子レベルの変化をもたらすことが明らかとなってきている。
2006年に厚生労働省は「妊産婦のための食生活指針」において、体格区分別妊娠中の推奨体重増加量を示している。それによれば妊娠中の体重増加は、
・BMI18.5未満のやせでは9〜12kg
・BMI18.5〜25未満の標準では7〜12kg
・BMI25以上の肥満では個別対応(おおよそ5kgを目安とする)
としている。
これまで我が国においては、"小さく産んで大きく育てる"ことがよいとされ、また妊娠中に母親の体重が増えすぎることのデメリットが強調されていたため、妊婦指導においても体重増加を抑制する方向にあった。今後は、妊娠中は適度な体重制限を行わず、妊娠前の体型に応じた適切な体重増加を目標として、妊娠中の栄養指導が行われるべきである。
【ヤングコーナー】
小児期発症1型糖尿病治療から生活習慣病対策を考える
菊池 透
新潟大学医歯学総合病院小児科講師
小児期発症1型糖尿病の重要課題は、もちろん生涯にわたる血糖コントロールの向上である。小児インスリン治療研究会のコホート調査から、日本人の小児期発症1型糖尿病でも、インスリンアナログ製剤の使用によりHbA1Cの改善傾向が明らかになった。
しかしながら、治療方法の進歩では解決できない問題が明らかになってきていると思われる。最近発症した1型糖尿病患児の母親が、「好き嫌いが多くて病院食は食べられないので、売店で好きなものを買ってきて食べさせてもいいですか」と聞いてきた。主治医としては、食べてもらわなければ、インスリン治療の指導もできないので、やむなく認めざるを得ない。しかし、このような患児、家族にインスリン治療だけ指導しても、いずれ血糖コントロールが悪化してくることは想像できる。
私は、1型糖尿病の発症を契機に、日常生活を見直していただきたいと考えているが、それができる家庭とできない家庭がある。その差はおそらく、発症前の家庭生活と関連している。しっかりした生活ができている家庭では、家庭全体に自己効力感があり、問題が起こったときにその高いポテンシャルが発揮される。一方、ポテンシャルが低い患児、家庭に対しては、医療スキルのほかに、自己効力感を向上させるような生活、活動支援が必要であり、キャンプや患者会の活動は、有用な方法である。また、このような支援は、肥満症や2型糖尿病に対する生活指導に準じたものである。
生活習慣指導は、肥満症や2型糖尿病に対してだけ必要なことではない。現在の日本では、すべての子どもたち、家庭に必要な指導ではないだろうか。健全な育児や生活習慣を支援することが、本人や次世代の2型糖尿病を予防する。また、糖尿病を発症した場合でも、良好な血糖コントロールの基礎になる。政治、行政にはすべての家庭が安心して子育てができる社会の実現を期待したい。
診察室だより 北から南から
群馬大学医学部附属病院産科婦人科
笠原 慶充
群馬大学医学部附属病院産科婦人科助教
“鶴舞う形の群馬県”(上毛かるたより)
首都圏の一部でありながらイマイチ認知度の低い北関東の一角に位置する群馬県は、総人口約200万人、総面積6,363km2、数少ない海なし県の一つです。
その中心に位置する県庁所在地、中核市である前橋市に1943年前橋医学専門学校が設置され、前橋医科大学、群馬大学医学部と名を変え、現在に至っております。
群馬大学医学部附属病院は20診療科、病床数715床を誇る県内唯一の大学病院であり、立地・交通・医療設備等すべての面から群馬県の中心としての役割を担っており、県内全般はもちろん、一部隣接する埼玉県や栃木県からも患者さんが来院される重要な基幹病院として機能しています。
約20年前、現在、当院内分泌糖尿病内科非常勤講師である小浜智子先生が赴任され、以来、多くの1型・2型糖尿病患者さんが、地域周産期母子医療センターである当院で分娩されています。しかし、小浜先生が赴任された当初は、「糖尿病患者は子どもを産んではいけない」という環境だったそうです。そのため、夜8時から、産科、内科、小児科、新生児科、眼科が集まり、勉強会や症例検討会を行い、その結果を一冊の小冊子にまとめました。その後、着実に分娩数を増やし、1型、2型、GDMを含めると、その数は数百例に及ぶと思われます。
平成19年度からは、新しく発足した糖尿病療養指導チーム(糖尿病専門医、産婦人科医、小児科医、眼科医、糖尿病認定看護師、助産師、栄養指導室等)の協力により、妊娠前の指導から妊娠中、分娩後の母児の管理に至るまでの継続したサポートをさらに強化することが可能となりました。
受診患者さんの増加により、院内、院外での患者さん同士の交流も自然と増えていき、妊娠中から出産後まで、さまざまな不安や育児に関して相談できる温かい、やさしい輪が広がっています。
深刻な医師不足、病院集約化の影響を受け、糖代謝異常疾患における当院の担う役割は今後さらに大きくなると思われますので、チーム医療のさらなる充実を図り、幸せな未来に向けてのお手伝いができればと思っています。